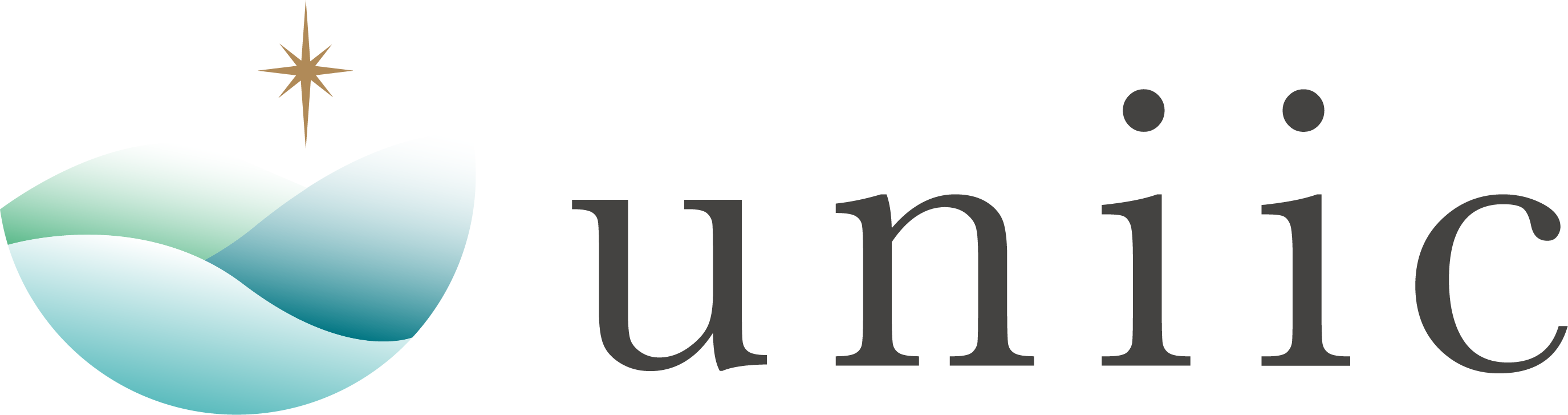はじめに
今回の「目的意識」で「自信の6要素」は最後となります。
ちなみに、英語表記は「purpose」です。
「パーパス」というカタカナ語も、ビジネス関連分野では日本語として見かけますが、これも前回の「対話力」と同じで、人によって微妙に解釈が違っている印象です。
あと「あなたのビジネスのパーパスは何ですか?」と聞かれても、大抵の場合は、少し困ってしまうのではないでしょうか?
質問そのものが漠然としている感じがしますし、就業形態によっては、簡単には答えられない質問です。
仮に自分で起業していて、パーパスを「自分のビジネスの存在意義」として認識していたとしても、「私のビジネスのパーパスは…」と答えるのは、何だか躊躇ってしまいそうです。
それよりも「あなたのビジネスはどんな事業内容なんですか?」「何を提供しているのですか?」といったように、幾つかの質問を通して、相手を良く理解しようとする方が、いきなり「パーパスは?」とか「存在意義は?」と聞くより失礼がないと感じますし、誤解なく話を進めることができるように思えます。
いずれにしても、今回の「目的意識(別名「パーパス」)」は、「自信」という枠組みの中での考察なので、組織ではなく個人レベルで捉えています。
ですから、性別、年齢、就業形態、家族構成… etc. 全て関係なく、誰にでも当てはまる内容となります。
このブログは、大きく分けて2部構成です。
1)「目的」について:「目的」を人生の中でどう位置付けるかという視点から、目的の捉え方と、“誤解“について書きます。
2)「目的意識」について:ここでの「目的意識」は、実は2種類あります。
ひとつは自分の「今」と「仕事」に直結する捉え方で、もうひとつは「本来の目的意識」です。
“本来の“というのは、これこそが「自信」に深く関わってくる部分だからです。
今回のブログは長いです。(いつも長いんですけど…)
では、お付き合いください。
「目的」をどうやって見つけるのか?
この質問に関しては、「目的」の捉え方をまず考えないといけないと思います。
「人生の目的」のように“大きなもの“になると、ある日「これこそ自分がすべきことだ!」と、まるで天からのお告げのように自分に降ってくるイメージで想像していたり、「真剣に(悩んで)探せば必ず見つかるはず」と思われている場合が少なくない印象です。
教職、医療、法曹といった業種は、「指導する」「命を助ける」「正義を貫く」みたいな文脈で、意義を見つけ易い職業かと思います。
そのため、こうした職業をいわゆる「天職」と感じて、心の底から望んでその道に進む人も多いのではないでしょうか。
他に、業種というより「社会格差をなくす」とか「貧困を撲滅する」みたいな、壮大な目標に向かって活動する人もいます。
こうした「人生の目的」(「存在意義」という意味でも)に関しては、Simon Sinekの「Start with Why」(邦題「Whyから始めよ!」)という著書がとても有名で、彼が提唱する「ゴールデンサークル」は様々なところで引用されています。著書以上に有名なのはTEDでの彼の講演だと思いますが、ご覧になった方も多いでしょう。
SNSでも、自己啓発系の投稿がたくさん見られます。
そういうのを見ると「人生とは?」「自己実現とは?」みたいことを、つい考えてしまいますが、人生について自問するのは、確かにそれだけでも意味はあると思います。
疑問があるからこそ、考え、答えを探し、その過程で理解も深まっていくわけですから。
ただ、「目的」がどこかに“隠されていて“いて、それを“見つければいい“だけだと思うのは間違いでしょう。(見つけるチャンスが皆無だとは言いませんが、極端に稀だとは思っています。)
そこで「目的」に関する、ありがちな誤解を2つ、下に書きます:
誤解(1)「目的」は探せば見つかる(見つからないのは、探さないから)
仕事に関して言えば、会社などの組織に属して働いている時に「自分の人生の目的は?」なんて考える余裕はまずないのではないでしょうか。
そこには、会社から定義された「目的」「目標」「課題」があり、自分はその与えられた枠組の中で役割に従って最善を尽くす、となるだろうと思います。
エンジニアが「自分の人生の本当の目的は、アーティストとして自由に創作をすることなんだ」と、ある日気がついて(?)退職届を出してしまったら?
何となく「それは危ないんじゃないか?」と思いますよね?
「私の夢はいつか小さな雑貨屋さんを開くことなんです」と言う事務職の人に、「素敵な夢だね!事務なんかやってないで、頑張って夢を実現した方がいいよ!」と言うのも違うと思うのです。(そんなのを安易に言ったら無責任ですし…)
仕事に関しては、「今自分が与えられている仕事に、どんな意味を見つけられるか」を考えるのが良いと思います。
故ケネディ大統領とNASAの掃除人のエピソードを知ってますか?
(伝説的で、ケネディ大統領じゃなくジョンソン大統領だったとか幾つかバージョンがあるのですが、そこは無視して…)
ケネディ大統領がNASAを訪問した時、
箒を手にして廊下を歩いている人に会いました。大統領は気軽に「君はここで何をしているんだい?」と聞いたところ、掃除人は「私は人類を月に送るお手伝いをしてるんです」と答えました。この掃除人は自分の仕事の目的(意味)を認識していた、ということです。
彼が掃除してくれるから、科学者もエンジニアも“本来の仕事“に集中できる、掃除をしてくれる人は、そこで働いている人に“働く環境“を作っている…と。
自分で自分の仕事の「意味」を認識し、自分なりの価値を“役割に沿って“提供できるかどうか。
そこに、仕事をする上での“目的意識“がかかっている、と言えます。「今の自分の職業で、この役割をこなすことで、価値、恩恵を受け取る人がいる。自分は大きな全体の中の、ひとつの大事な役割を受け持っているんだ」という意識が大事だと思うのです。
実際に、恩恵を受けている人はたくさんいるはずです。
どんな仕事でも「意味」はありますから。
…というよりも、「意味のない仕事なんてない」と思いませんか?誤解(2)「目的」は“唯一普遍“
“ごく普通“だと思っている自分の人生さえ、実際には色々な要素から成り立っています。
「人類の救済」みたいな大きな目標に向かわなくても、悩みや考え事には不足しません。自分の人生。
仕事とプライベートという2つの種類だけではなく、更に細かく分かれています。仕事なら、業務内容そのもの、自分が属する部署とそこにいる人たちとの関係、自分のキャリアなど多岐にわたっていますし、プライベートでも、個人としての趣味もあれば、家庭での役割もあります。
さらに、家庭での役割も、親に対する子供として、配偶者として、子供がいれば親として、と更に細分化されます。しかも、人生の中には様々な“区切り“があります。
子供から大人になるのは、それだけでも変化ですが、成人になるのは社会的にも大きな区切りになります。
大人になってからも、仕事が変わったり(転職しなくても部署の移動とか)、キャリアアップして役割が増えたりもします。人生は変遷です。
そんな流れの中で「唯一普遍の目的」なんて無理だと思いませんか?
18歳の時の「人生の目的」と、25歳の時の「人生の目的」
同じですか?
40歳の時は?
60歳ではどうですか?人は成長します。
目的も変わります。人生に「唯一普遍」の目的はない、と思うのです。
固定観念に囚われずに、「今の自分の役割が持つ意味」に意識を向ければ「目的」が見えてくるはず、ではないでしょうか?
「目的意識」は必要なのか?
日常生活では、好むと好まざるに関わらず色んな「必要な事」が溢れています。
それをいちいち「これをする目的は?」と考えていたら、何もしないままで1日が終わってしまいそうです。
これまで見てきたように「今の自分の仕事や役割に見出せる“意味“を、誠心誠意体現するのが、自分の“目的“だ」とするのは、有意義であるだけでなく、仕事だけではなく、日常生活のあらゆる作業に応用の効く、とても大切な視点です。
でも、この文脈で「目的意識」は、「持たないといけないもの」なのでしょうか?
率直に言って、「持たなければいけないもの」ではない、と思います。
ただ、「あった方が生き易くなる」とは思います。
なぜなら、目的を自分で定義すれば、その作業(仕事)は「自分事」になるからです。
やらなければいけないから…。
そうしろと言われたから…。
これだと、ヤル気もなかなか起きないですし、自分が苦しいだけです。
単発ではなく、日々繰り返される作業ならなおさら、疲弊していきます。
ある研究では、目的意識を持って生きている人は、そうじゃない人と比べて、早逝リスクが15%も低いそうです。
自分がしていることに意義を見出して「目的意識」を持った方が、健康で長生きできると言えそうです。
ここでの「目的意識」は、別の言葉で言えば「その仕事の意味を認識する」です。
次に書く「目的意識」は、これまで書いてきたのとは少し違う様相のものです。
そして、これこそが今回のブログで書きたかったことになります。
本来の「目的意識」とは何か?
これにも「目的意識」という名称を使っていますが、あえて別の表現をするなら、シンプルに「自分らしい生き方」が合いそうだと思っています。
具体的にはこんな感じです:
嘘のない、
本来の自分であろうとすること。特別でユニークな自分らしさを活かそうとすること。ここで使う「目的意識」は「自信の6要素」の第1項目「自分らしさ」で書いた内容に密接しています。
ポイントは、自分が「何をするか?」ではなく、「なぜそれをするのか?」そして「どうそれを行うのか?」なのです。
(ここでSimon Sinekの講演を思い出しください)
同じ仕事をしていても「全く同じ」ということはありませんよね。
会社で担当が変わって引き継ぎが行われた時、業務内容は“前と同じ“に遂行されているかもしれませんが、担当者が違うだけで、何かか“違う“ような感じを受けませんか?
本来の「目的意識」は自分らしさに根差します。
それは自分のアイデンティティと切っても切れない関係にあるのです。ここで、私自身を例にしてみます。
私は20年以上にわたりビジネス、学術関連の通訳をしてきました。
国際的に「ネイティブレベル」と認められた「C2」認定を受けているので、それなりに複雑な案件が多かったです。私は通訳の仕事を「日本語を外国語に、外国語を日本語にする作業」としてではなく「相互理解の橋渡し」とみなしていました。言葉(と文化)が違う人同士を、川のこちら側とあちら側にいる人同士とします。この人たちは、そのままでは出会う事ができません。私は、川の両側にいる人たちを繋ぎ、相互理解の機会を作る「橋」が自分なんだと思って、仕事をしていました。
異文化間の“橋“として、人と人を繋ぎ、誤解のない世界を創りたい 自分の人生で集めた、知識や能力は「道具」であって、それ自体は目的ではありません。
例えば「通訳になるために外国語を勉強する」というのは、一見すると目的意識があるように見えるかもしれませんが、最終的な目的では絶対にないのです。
・なぜ通訳になるのか?
・通訳になって何を達成したいのか?
・どんな通訳でありたいのか?それに対する答えが、自分の「目的意識」になります。
「異文化間の“橋“として、人と人を繋ぎ、誤解のない世界を創りたい」が私にとっての通訳としての「目的意識」であったように、他の通訳にはその方の「目的意識」があると思っています。
そして、どの目的意識もユニークで、どれも「正解」です目的意識は「絶滅の危機に瀕している動物を助けよう」みたいな、壮大なものではありません。
そうした目的意識は、往々にして「こうあるべき」「そうするのが正しい」という考えから発していることが多く、「自分のユニークさ」に根ざしていないからです。ここで言う「目的意識」は、「自分が自分であるために、他の在り方は考えられない」という、「自分ならではのユニークさを生きる」という確かな意志なのです。
どうしたら「目的意識」を自覚できるか?
まずは「自分らしさ」です。
とはいえ、自分らしさをしっかり認識するのは、「自信の要素」の中で最も難しい部分だと思います。
自分についてもっと詳しく知りたい。
自分の可能性を伸ばしたい。そんな風に思うのは、とても自然なことではないかと思うのですが、自分に向き合うのは楽しいことばかりではなくて、自分の中にある(人間らしい)醜い部分も、弱い部分とも向き合わなくてはいけません。
しかも、自分のことだからこそ、あまりにも無意識/無自覚過ぎて、自分では思いつかないような面もあります。ただ知識として「私ってそういう長所/短所があるんだよね」と確認するだけでは不十分です。
それが何を意味し、周りにどんな影響を与え、さらにそれが自分にどんな風に返ってくるのかも含めて、「自分の在り方」そのものを見直さなければいけません。
(想像以上に時間とエネルギーのかかることですが、するだけの意味はあると、私自身の経験からも確信しています)決して簡単ではありませんが、これが分かれば、あとは比較的スムーズに進みます。
…………………………
ここから先は「自信の付け方#3:自分らしさ」の繰り返しになってしまうので深くは書きませんが、例えば、自分らしさが「飽くなき探究心」にある場合はどうなるでしょうか。
研究者として学術機関にいる人や、企業のR&Dで働いている人はもちろん「飽くなき探究心」に合ってるだろうと想像がつきます。
でも、営業職なら?
「自分が提供する製品/サービスをとても詳しく知って、顧客により良い説明ができる」かもしれないですし、「顧客についてとても良く知っているので、最適の製品/サービスを提案することができる」となるかもしれません(もちろん両方もあり得ますよね)。他にも様々な仕事に当てはまると思います。
「飽くなき探究心」というユニークさの人は、きっとその情報収集の能力と、情報量の多さで業種役職に関係なく素晴らしい成果を出せると思います。
そして、仮に、自分の仕事が「最近何だか思うようにいかなくて…」と悩んだ時でも、自分のユニークさを思い出して「自分は何かを追求する熱量が高い。このエネルギーを活かせるのはどこ?何を、どうすればいい?」と、今現在抱えている仕事に当てはめながら考えてみると、きっと進む方向が見えてきます。
「目的意識」が自信に与える影響
ここで、また私の話に戻りますが、通訳として仕事をする際に、「橋に人格はない」くらいに思ってましたし、実際に「通訳は黒子。顔も名前もないんです」とよく言っていました。
個人の自我(エゴ)はどうでもいい。
個人の小さなエゴより大事なのは、目的の達成。仕事の後で通訳の出来栄えを誉めてもらっても、あるいは貶されても、その一瞬は嬉しかったり申し訳なかったりしますが(感情の波です)、他人の評価は、実際のところどうでもいいのです。
大事なのは、
・自分の持てる能力を惜しむことなく出し切ったか?
・“橋渡し“ができていたか?
・相互理解に繋げる事ができたか?という、自分の目的意識を基準とした自己評価です。
達成できていれば、通訳として顧客にどう評価されようが、正直なところどうでも良かったですし、どんなに誉めてもらっても自分で納得できなければ、悔しいですし、次回の課題として残るのです。
自分に嘘は、絶対につけません。
(注:「相互理解」は仲良くさせるという意味ではありません。双方が相手方を理解した上で「相容れない」となれば、意見の相違で決裂することもありますし、それぞれの事情で会話が平行線を辿ることもあります。何語であろうと、通訳がいてもいなくても、会話はその場、その場での流れがありますよね。)
「目的意識」は自分の本質に直結するものです。
そして、それが本質に近づけば近づくほど「使命感」とも呼べるものに変容します。自分の全ての意識を、それに向けると、周りの雑音は消ます。
「目的意識」は、自分の“自信のなさ“を超えていきます。“できる/できない“ではなくて、“する以外の選択肢が残らないのです。
ここまで来れば、それはもう「自信」と同じです。
…………………………
自信を持つのは簡単ではありません。
自信があれば、怖いものがなくなるわけでもありません。でも、自分を信じることは可能なんです。
自分を認めて、自分を信じていいんです。目的、そして目的意識。
それは自分という「個」よりも遥かに大きなものです。自分らしさに根差した、本来の「目的意識」は、自分の生き方に、自分でも驚くようなエネルギーを与えてくれます。
そのエネルギーは、最強の自信になると、私は信じています。さいごに
「自信の6要素」を使って見てきた「自信の付け方」もこれで一通り終わりました。
あまりにも長くなってしまったので、最後のまとめとして「このブログシリーズで伝えたいのは、簡潔に言えば何か?」というのを改めて振り返ってみます。
…………………………
「自分を疑って初めて、本当に自分を信じることができる」
そう思います。
何も疑わずに「自分は何でもできる」と思い込んでいるのは、自信ではなく、単なる物知らずの“無謀さ“です。
痛みを知る人ほど優しい人が多いように、自分に自信がなくて、自分を疑う人ほど、きっかけさえ掴めば、自分を信じることができます。
「自己肯定感を高める」という表現がありますが、「自己を肯定する」だけでいいと思うのです。それから、周りの人は時に無責任なものです。
「あなたは…すぎる」(話しすぎる、静かすぎる、細かすぎる、etc)
「あなたは…がない」(スキルがない、経験がない、社交性がない、etc)この2つの文脈で、いろんな批評/批判をしてくるでしょう。
言われれば、恥ずかしかったり嫌な思いをしたり、自分を責めたり落ち込んだりして、自信をなくしてしまうことがあるだろうと思います。
でも、他人の心無い言葉に「自分の心を支配される」いわれは全くありません。
単なる批判は、一過性の嵐と同じです。知らないことは不安を生みます。
そして不安は自分の足元を揺るがせます。己を知る。
周りを知る。そして、可能性を捨てないでください。
何事にも「違う面」があります。
それは、もしかしたら、とても興味深いものかもしれません。このブログシリーズに限らず、私が最もお伝えしたいことは、こうです:
自分は、
自分らしくあればいいんです。自分であることに、誰の承認も、評価も要りません。自分を輝かせるために、誰かから“照明“を当ててもらう必要はないのです。自分こそが、輝く光です。こうして私を見つけて、私のブログを読んでくださって、とても嬉しいです。
ありがとうございます。私がかつて通訳として異文化の「橋」だったように、私の今の「目的意識」は、あなたが「本来の自分と(再び)出会うための橋」であることです。
次回のブログは、このシリーズの「総まとめ」のようなものを考えています。
ワークショップの告知もあります。
疑問、気になること、なんでも教えてください。
次のブログで一緒に考えましょう。次回もこれまで通り金曜日に更新します。
またお話しましょうね。
Tagged communication, confidence, purpose, self-awareness, Success, uniqueness, パーパス, 目的意識, 自分らしい生き方, 自分らしさ, 自分を輝かせる