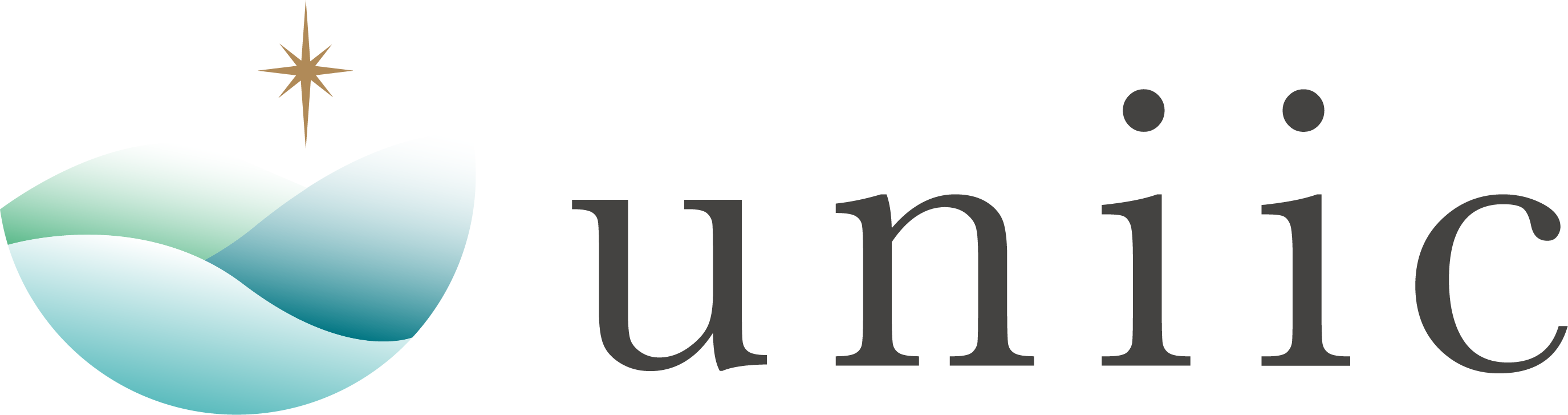はじめに
「自信の6要素」は日本語表記のほか、図の外枠に英語でも書いてあります。
これは、その方が「なんとなくカッコイイから」ではなくて、日本語の意味と、英語の意味の両方を加味したかった、という欲張りな理由です。
また、図なので、簡潔な表記にしたかったというのもあります。

今回は5つ目の要素「対話力」で、外側の英語表記は「communication」です。
ここで「なんで“対話力“? “コミュニケーション“で良くない?」と思った人もいるのではないでしょうか?
「コミュニケーション」という単語は、十分に日本語として通用します。
割と何気なく日常で使っていますし、疑問に思われたとしても無理ないと思います。
むしろ、このブログタイトルから「どうして“communication“が“対話力“なの?」と疑問に思っていただけたら嬉しいです。
「対話力」は、もちろん“communication“の訳ではありません。
それどころか、広辞苑にも載っていない日本語ですし、ビジネス関連の記事で稀に見かける比較的新しい言葉です。
とはいえ、「聞いたことない」というほど珍しい言葉でもないと思います。
なぜ「コミュニケーション」ではなくて「対話力」なのか?
「対話力」をuniicではどう捉えて使っているのか?
そして、それがどんな風に「自信」にとって大切な要素なのか?
…といった内容を中心に、今回は書いていきます。
「コミュニケーション」と「コミュ力」
プライベートよりビジネスシーンで使用される頻度が高いと思うのですが、「コニュニケーション」は「相互連絡」や「情報の共有」といった意味で、「コミュニケーションをとる」は「(特定の事柄についての)共通認識を図る」といった意味で使っているのではないかと思います。
これは、仕事を円滑に執り行うために必要なことですし、そうやって連絡を取り合うことで、人との繋がりもできますから、事務的な「情報共有」という目的以上の意味がある大切なことだと思います。
また、「コミュ力」という短縮系で良く知られた「コミュニケーション力」ですが、これもビジネス関係の書籍や記事で良く見ます。
でも、コミュニケーションとしての、いわゆる“報連相“ができている人を「コミュ力が高い」とわざわざ言うでしょうか?
なんとなく違うような気がします。
ところで、自分の周りに「コミュ力が高い」と言われている人はいますか?
その人は、どんな特徴があるでしょうか?
あくまで想像ですが、「コミュ力が高い人」と言う場合は、こんな感じではないでしょうか?
人見知りしない。
他者との接触や交流に抵抗がない。ビジネス上のお付き合いや必要とされる連絡や情報の交換だけではなく、いろんな人と連絡をとり、交友関係が広い。社交的な人。こういう人は目立つ人でしょうし、人気もあると思います。
「コミュ力」の高低に注目されるのも無理ないです。だからなのでしょうが、「コミュ力を上げるにはどうすればいいか」というHowTo系の書籍や記事は、「自信を付けるには」や「自己肯定感を高めるには」というのと同じように、たくさん存在します。
ただ率直に言って「それが簡単にできていたら苦労しない」のです。
もし誰にでも自然に無理なくできるものなら、こんなにたくさんの書籍や記事があるはずもないでしょう。さらには「コミュニケーション力」に関して、ひいてはビジネス界隈で使用される「コミュニケーション」に関して、意義、定義は使う人によって違いがあるように見受けられます。
そこで、ビジネス的認識から一旦離れて、広辞苑を確認すると、広辞苑では「コミュニケーション」をこう定義しています。
社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達。言語・文字その他視覚・聴覚に訴える各種のものを媒介とする。「マス‐―」「会社内の―が悪い」
ここで「“コミュ“力の高い人」を広辞苑にならって書き換えてみると…
「“知覚・感情・思考の伝達“力の高い人」となります。伝達は「伝わる」と「達する」です。
広辞苑でも、伝達は「命令・連絡事項などを伝えること。つぎつぎに伝え届けること」とあります。
ということは、内容が相手に「伝わり」、相手にきちんと「達して(届いて)」なければ伝達ではない、となりそうです。では、一般に「コミュ力が高い」と言われている人は、それが出来ている人でしょうか?
その人が、どんなに明るい性格で交友関係が広くて話題が豊富でも、「自分の発信」で留まっているなら、本来の意味としてのコミュニケーションは不十分です。(何となく、送信したと思ったメールが、実はアドレス間違いで相手に届いてなかった、みたいな連想をしてしまいます…)
コミュニケーションは「伝達」であり、そのポイントは「相手に届くかどうか」にありそうです。
コミュニケーションの錯覚:外向性と内向性
このブログで「コミュニケーション」というカタカナ語をあえて避けている理由は、
「コミュ力の高さ」と「外向性」を取り違えてないだろうか?
という懸念もあるからです。
外向性も内向性も生来の気質ですから、努力や学習の問題ではありません。
もしコミュニケーションが、「誰とでもすぐに仲良くなれる」などの社交性や、いわゆる「明るい性格」と言われる外向性に左右されるのであれば、内向的な人間は始める前から「コミュニケーションができない」と言われたようなものです。
そんなはずはないですよね!
本来のコミュニケーションは、相手に何かを伝える時に「何を媒体として」「どう伝えるか」であり、それも、自分のためではなく「相手に届けるため」です。
言葉だけでなく、コミュニケーションは五感全てを情報チャンネルとして使います。
外向・内向で決まるものではありません。
例えば、なんとなく元気のない人に「どうしたの?そうだ、今日一緒にご飯でも食べに行かない?悩みがあるなら相談に乗るよ」と誘うのもひとつの形でしょうし、何も言わずに机の上にお菓子を置いてあげるのもコミュニケーションの形だと思います。
大事なのは「コミュ力」の名称で広まってしまった(ように見える)「コミュニケーション=外向」の誤解から離れ、「自分らしいコミュニケーション」を目指すことです。
そのために「自分はどんな人間で、相手とどう向き合うのか」という姿勢を、改めて考えてみる必要があると思うのです。
自分には「自分らしいコミュニケーション」が必ずあります。
そして、自分らしいコミュニケーションを行う能力を「対話力」とuniicでは呼んでいます。
(注:ここで「能力」というのは持って生まれた才能というより、「磨けば光るもの」とか「筋肉のように鍛えられるもの」と解釈してください)
「対話力」とは?
このブログシリーズ「自信の付け方」で、これまでも見てきましたが、他者との関わり方次第で、自信は生まれも消えもします。
社会生活の中で「会話をする」機会はたくさんあります。
どの場面でも(当然ながら)「相手ありき」です。
講演やプレゼンテーションのような、片方が話して、もう片方は聞くだけの状況でさえ、非言語レベルでの会話は進んでいます。
つまり「私たちは常に“対話“をして生きている」と言えます。
uniicでは、「対話力」を次のように捉えています:
・言語・非言語を介した交流の中で
・情報の交換と伝達を互いに行いながら・自分を発信し・相手を知り、理解し・相手の価値観を尊重しつつ・相互理解につとめ・信頼関係を作る能力「対話力」は見ての通り「対話+力」です。
ちなみに「対話=dialogue」は語源的に「dia (cross) + logue (talk)」だそうです。
会話がクロスするから「対話」なんだと納得がいきますが、この言葉から「エネルギー交換」を連想してしまいます。人がもつエネルギーが感じられるのは「感情」ではないでしょうか。
会話を通して、自分と相手の間に生まれる感情(エネルギー)が行き来する…そんなイメージが浮かぶのです。
ですから、対話力の「力」という字には、「能力」という意味の他に、エネルギーとしての「力」という意味も込めてあります。「対話力」が目指すもの
「対話力」で目指すのは、言語・非言語を媒体として築く信頼関係です。
私たちが誰かと話すとき、そこには「情報交換」と、その結果としての「情報の共有」という目的があります。
特定の情報が含まれた仕事での会話だけでなく、プライベートで友達とカフェで会って話す時にも、お互いの現状を確認したり、噂話として共通の知人の近況を伝えたり、面白かった本/映画/聞いた話/etcを教えたり、最近の悩みを相談したり…、多くの「情報」が溢れています。
仕事でも、プライベートの会話でも、根本的な部分では何も変わらないと思いませんか?
…………………………
相手の話からわかるのは「その人の価値観」です。
友人であれば、「相手の価値観を知っている。それは自分の価値観と同調している。相手は自分の価値観を受け入れている」という「価値観の擦り合わせ」が過去の数え切れない会話を通して出来上がっているので大きな問題は起きませんし、その上で相手が「(自分を)わかってくれる」という安心感があります。
つまり、信頼関係が出来上がっているのです。
初対面の相手に対しては、そうはいきません。
誰かと初めて会う時、多少は緊張しませんか?
仕事では、話すべき内容はあらかじめ分かっているので「何を話そうか?」と悩むことはないと思いますが、それでも相手と良い関係性を作りたいと思うと、会話を進めながら手探り状態になるのではないかと思います。
相手を理解しようと質問攻めにするのも良くないですし、自分を分かってもらおうと話してばかりいるのも問題です。
また、相手に気に入られようと迎合したり、自分に有利に話を進めようと誘導したりする行為は、その場での会話目的が表面上は達成できたとしても、信頼関係は築けないでしょうし、安心感も生まれないので、結局は自分が疲弊するだけだと思います。
「相手から良く思われたい」という気持ちは、とても良く理解できます。
でも、それが会話のモチベーションになると、本来の目的と違う方向に行ってしまいそうです。対話力の「力」は「自分らしさに留まる力」とも言えます。
自分が本当に「自分らしい」状態であれば、他者からの評価は実は気にする必要のないはずのものです。
(ブログ「自信の付け方#3- 自分らしさ」参照)嘘のない自分。
自分の価値観を言行に反映させる自分。それは「信頼に足る人」に見えませんか?
対話力は「在り方」
例えば、会話の手法として「オープンエンドの質問をする」というのがあります。
その方法や効果も、探せばたくさん見つかります。そういうのを読むと、確かに納得はできます、…技術的には。
会話テクニック重視の記事では「相手からより多くの情報を引き出すことができます」といった説明も見られました。
確かに「情報を得る」のだけが目的なら、そうかもしれません。
会話の相手が「情報源」でしかないのなら、です。
得たい情報を引き出すために、どんなオープンエンドの質問をしようかと、相手が話している最中も、頭の中で次の質問を考えたりもするでしょう。でも、本当に意識すべきは「オープンエンド質問の仕方」ではなくて、「なぜオープンエンドの質問をするのか?」ではないでしょうか?
…………………………
私たちが向き合っているのは「人間」です。
「世界に1人しかいない、その人と知り合う『一期一会』の機会なのに、情報源扱いでしかないの?」と思ってしまうのです。
ですから、uniicでは、嘘のない本来の自分のままで、正しい心構え(マインドセット)で相手に向かい合うなら、対話においてのテクニックは二義的だと考えます。
・相手に対して敬意があれば、礼を失しません。
・相手に対する素直な好奇心があれば、自然にオープンエンドの質問が出てきます。どんな答えでも、自分には相手を知る嬉しい情報です。・相手との時間を大切に思うのなら、相手に集中します。スマホも気にならないですし、話を聞きながら『後で…しなきゃ』と別の予定を気にしたりもしません。・相手の話に集中するので、話の「流れ」に乗ります。話の腰を折って自分が「話したい事」に持っていきません。どんなに有効なテクニックでも、それがどんなに理屈にあっていても、「本物」でなければただの「ふり」です。
そして、「ふり」は「対話力」には必要ないのです。…………………………
このブログシリーズで「自信は自分を信じること」と書いてきました。
対話力は、他人の評価に左右されない「自分らしさ」を保ち、対人不安を減らす力となります。
さらには、「人と信頼関係を築く」力であり、「信頼関係を築く姿勢がある」という自分の能力の肯定です。
「自信の6要素」は全てが相互に作用しあっています。
・自分の価値を認識し(自分らしさ)
・表面的な感情に流されず(感情)
・気後れせずに、好奇心を持って(ポジティブ思考)
・その状況に適った姿勢で(姿勢)
・会話を通して相手との信頼関係を築く(対話力)と、繋がるのです。
対話力は単なる「コミュニケーションの能力」ではなく、「自信を持って相手とコミュニケーションするための在り方」です。
さいごに
「聴く」は「話す」より難しいかもしれません。
相手の話をしっかり聴くには、自分らしくあると同時に、自分を忘れるのが大事なのかなと思います。誰の言葉だったか忘れてしまったのですが、「対話力」での「聴く力」をとても簡潔に表現しているのを聞いたことがあります。
“Mind open, mouth shut down!”
…ということで、今回はこの辺で。
また、お話しましょうね。
Tagged communication, confidence, self-awareness, self-confidence, self-value, Success, uniqueness, 自分らしさ